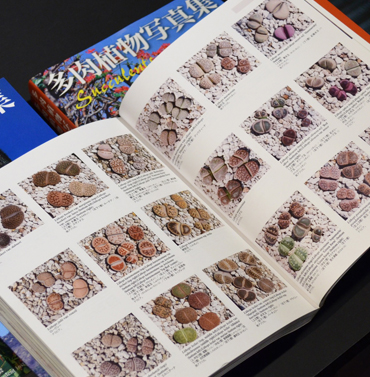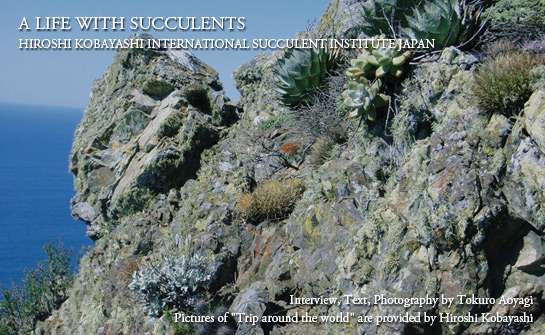過去にサボテンブームというものが何回かあって、私より10歳くらい下の今の団塊世代、64〜65歳くらいの人が、一番サボテンに狂った方だと思います。
その人達も中学生くらいで夢中になったはずです。そう言う人達が今も業界に残っていて、それぞれ活発に動いています。大量に栽培して業者に販売したり、
仕事になってしまっている人達もたくさんいます。
僕自身も学生の頃はもちろん、会社入ってからもずっと多肉植物を追いかけていました。東京の自宅にビニールハウスも作りました。当時はビニール自体もあまり普及してなく高価で、
資材集めも大変でした。温室大工さんというのがいて、頼んで木製のハウスを作りましたが、ヒーターもなくて加温もできないから苦労しました。
その頃になると、あちこちにあった卸業者さんにも行くようになりました。そういうところで見たのが輸入品です。輸入品は欲しくてもなかなか手に入りませんでした。欲しいと言うと「10人待ってるから売れない」とか言われて、頭にきてしまいました。ですが、そういった業者も自分では輸入できないのです。調べてみると、どの業者も貿易商に輸入してもらっていたのが分かりました。
特に当時は語学や為替の問題があり、海外とのやりとりの経験が無い業者の人にとっては、輸入というだけでハードルが非常に高かったのです。ですから元々海外から楽器の輸入販売をしていた植物好きの社長が、サボテンや多肉植物も輸入して、そこから業者も買うといったようなケースが多かったです。
そうなると輸入品はどうしても少なく、その割に高度成長で金を出す人はたくさんいたので、なおさら業者は簡単に売ってくれません。
当時は旦那衆と呼ばれる裕福な人達や、医者とかお坊さんとかが愛好家に多くて、彼らはお金に糸目をつけません。
そんな中、自分で外国の雑誌や資料を色々集めて、ついに輸入元を突き止めました。当時、1ドルが360円。銀行も個人には一定額しかドルを売ってくれないので、
お金も自由になりません。身分証明書や住民票なども必要で、中々スムーズにものごとが進みません。それでも何とか輸入元に手紙を出してやりとりをして、
南アフリカとオランダから輸入する事に成功しました。それが50年程前、22〜23歳の頃です。そこからだんだんとメキシコなど違う国にも広げていきました。