

「憂歌団は“家”みたいなもんやと思ってた。でも、やりたいことがなかなかやれなくて…。僕は僕を生きてる。
ほんまに気持ち持ってやらな恥ずかしい。アカン。楽しく出来んのやったら、そんな“家”に帰らんでもええんかもなぁと思ってました。
だから、内田がバンド辞めようと言った時、嫌なんと嬉しいのとが半々でしたわ…」。
ほんまに気持ち持ってやらな恥ずかしい。アカン。楽しく出来んのやったら、そんな“家”に帰らんでもええんかもなぁと思ってました。
だから、内田がバンド辞めようと言った時、嫌なんと嬉しいのとが半々でしたわ…」。
98年、日本屈指のブルースバンドとして20年以上に渡りシーンを牽引してきた伝説のバンド、憂歌団は休眠する。その憂歌団のリードヴォーカルとして絶大な人気を誇ってきたのが木村充揮さんだ。“天使のダミ声”と称される唯一無比な声の魅力、圧倒的なブルースフィーリングで、日本最高のヴォーカリストの一人として高く評価されている。以前、ネペンテスの代表である清水慶三さんにインタビューした際に、影響を受けた人物について聞いてみたところ、プロ野球選手の長嶋茂雄さんと並んで名前が上がったのが、この木村充揮さんだ。当然、ファッション関係の人が出てくると考えていただけに、その事がとても印象に残っていた。ネペンテスを創り出した清水さんが大ファンで、ライブにもよく足を運ぶという木村さんとはいったいどんな人なのか…。様々な想像を巡らせながら、南巽の駅に降りた。
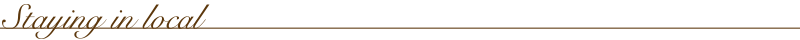
1954年に大阪市生野区で生まれる。大阪の生野区というとコリアンタウンがあったり、町工場があったり、小さな住宅が密集していたりと、いわゆる大阪の下町のひとつである。木村さんは今も生野区に住んでいて、大御所だからといって、特に高級住宅地へ移るといったこともない。「じいちゃんから、ばあちゃん、おっちゃん、おばちゃん、子供まで、色んな世代やタイプの人間がおる下町がホッとする。ほら、“おそうじオバチャン”という歌も、おっちゃんやったらウケんかったやろうね。何かそうゆう感覚って下町にありますやろ」。7人兄弟の4番目で、歌は幼稚園の頃から好きだったそうだ。「オヤジがギター持っててね。こっそりと何かよう弾いてましたわ。ギターは中学二年の時に兄ちゃんが金払たるからゆうて、1年くらい習わしてもろて、ピアノも妹が習いに行っとったからついでにね。特に音楽の影響を受けたんは、10歳上の姉ちゃんかな。小学生の時に近所の喫茶店によく連れて行ってもらって、そこでシャンソンやらカンツォーネやらがかかっとってね。レコードもいっぱい持っとったんで、ラテンやジャズのレコードから西田佐知子やフランク永井なんかの歌謡曲まで色々聴かせてもらって。それから、親戚のおっちゃんと新世界にご飯食べに行って、商店街で流れてた越路吹雪の歌。確か“サン トワ マミー”やったと思いますが、わーっ、ええなぁと感動したんをよく憶えてます」と、木村少年は、周りから自然と入ってくる音楽を素直に受け止め、“何かええなぁ”という感覚を体に刻み付けていった。ちなみに、当時、音楽のテストでは、ピアノやギターを習っていたおかげで筆記は得意だったそうだが、意外にも歌の方は点数が悪かったらしい。「普通の人よりちょっとキーが高かったみたいでね。だから自分で歌が上手いっていう認識はなかったんですわ」。そして、中学に入ってからは、ビートルズやローリング・ストーンズ、ジミー・ヘンドリックス、クリームといったロックを聴く様になる。「友達の家にごっついステレオがあって、ストーンズのテルミーを聴かせてもろた時にはビックリしました。ドーンと音がなって、まるで目の前で演奏しとるみたいで。その友達の家で、当時のロックを色々聴いたり、みんなでギターを演奏したり…。高校は工芸高校の美術科だったんですけど、それもその友達が『お前は絵上手いし、工芸高校にしたら』って薦められて決めたんですわ」。

木村さんはインタビュー中に“出会い”という言葉をよく口にする。「自分でバッと行くタイプというより、出会いがあって自然とね。昔からですかね」。生きていく上で必要な知識も、その自然な出会いから生まれた人間関係から得ることができた。「僕は本なんかも全然読まないんですよ。知識は周りの人が教えてくれますやろ」。小さい頃はどんなお子さんでしたか?との質問には、「素直で良い子でしたよ。普通に近所の子と将棋したりね」との答え。幼少の頃より、素直で飾らず無理のない感じを続けてきたことがよく分かる。普段から人より抜きん出てやろうとばかり考えていると、より情報で武装して、色んな物事に対して自分を無理に反映させようとしてしまうもの。木村さんのサラッとした生き方はとても上品で、それが歌やステージングにも表れている。進学先の大阪市立工芸高校では、憂歌団のリードギター、内田勘太郎さんと運命の出会いを果たす。「内田と友達になって、どっちも好きな音楽が似とってね。そのうち内田の方がブルースにどんどんハマって行って、僕もだんだんブルースってええなぁと思う様になったんです。学校にギターを持ってくる様になって、毎日、実習室に行っては、ギターを弾いて遊ぶようになった。僕が3コード弾いたら、内田が適当にブルースを弾いて、面白いやん!みたいにね。ほんで最初は内田が歌ってたんやけど、ある時、お前も歌ってみろって言われて、ポンと歌ってみたら、ええやん!てなって…。それからですわ、歌う様になったんわ」。


セールで売り出されていた安い1200円のアコースティックギター。内田さんが独学で習得したオープンチューニングやボトルネック。耳で憶えて書き留めて歌った昔むかしのブルースのレコード。B.B.キングのライブ。二人でアコースティックギターを持ち寄ってできる遊びは、ブルースの根本であるところの自由で気ままな楽しさに溢れていた。「ブルースって、3コードでできるから簡単なんです。決まり事が少ないから自由やし、だから好きな様に楽しめる。要はスイングできるかとうか。自分のスイングができるってことは、自分の楽しみを見つけること。体から出てこんとアカンのです。気ままに、自分の体格とか風土なんかから生まれてくるもんなんです。ブルースって生活の歌。ありのままの音楽なんですわ」。木村さんの歌の素晴らしさは、まさにそうゆうトコロにあって、曲順も決めないし、リハーサルもしないし、ギター1本だし、演歌も歌うし、歌謡曲も歌う柔軟さで、とにかくオールフリー。とことんシンプルでルールもなくて、全てが一発勝負である。「ライブで今日は良かったなぁと思っても、また次落ちることもあるしね。そうしたらまたあげたいって思いますやん。良かったことが残ってたら、今をちゃんとできようになる」。
観客に裸同然の自分をさらけだし、今をどれだけ大切にするか…。一見、木村さんの“酒を片手にギャグを飛ばしては歌う”というスタイルは、面白いおっちゃんといったイメージも強い。実際それが面白いのは事実だが、そのスタイルは一回一回のライブをより良いものにするために、自然と辿り着いたスタイルなのだろう。自分がありままで気持ち良く歌う、だからこそ観客もすっと入り込んで楽しめる。そこにアーティストとしての優しさとプロ意識を強く感じることができる。
観客に裸同然の自分をさらけだし、今をどれだけ大切にするか…。一見、木村さんの“酒を片手にギャグを飛ばしては歌う”というスタイルは、面白いおっちゃんといったイメージも強い。実際それが面白いのは事実だが、そのスタイルは一回一回のライブをより良いものにするために、自然と辿り着いたスタイルなのだろう。自分がありままで気持ち良く歌う、だからこそ観客もすっと入り込んで楽しめる。そこにアーティストとしての優しさとプロ意識を強く感じることができる。
高校を卒業後は、京都で起こったブルースブームに乗って、京大の西部講堂などでライブをするようになる。ちょうどその頃からベースの花岡献治さん、ドラムの島田和夫さんが加わって憂歌団は四人組となり、75年に“おそうじオバチャン”でレコードデビュー。日本のブルースシーンの夜明けとも言える時期から既に、大きな存在感を発揮していた。
デビューアルバムとなる“憂歌団”は、まさに楽しくてしょうがないという気持ちがストレートに伝わってくる傑作だ。元々、そのライブのスゴさからメジャーにまで上り詰めたバンド。本編90分、アンコール90分といった、今では信じられない、筋書きのないパフォーマンスを披露し続けるなど、まさに唯一無二のブルースバンドとしてシーンに君臨した。また、88年に日本人バンドとして初めてシカゴ・ブルース・フェスティバルにも出演。日本にも本物のブルースバンドがいることを本場アメリカで証明してみせた。
「当時は日本語でブルースっていうのはあんまりなくて、ブルースは外国のモノという先入観があった。日本語のブルースはダサイっていうムードもあったけど、僕はそういう考え方の方がダサイ様な気がしたんです。日本語の方が歌う方も気持ちが入るし、聞く方もわかりやすいしね。とはいっても、アメリカのシカゴでやった時なんかは、日本語で歌っても現地の人は楽しんでくれたし、言葉を超えたところで分かりあえるんやとも思いました。イイものはイイ。そんなのをあっちへ行って実感しましたね。他に面白かったんは、大阪でいうところの青空カラオケみたいな感覚があっちにもあって、街のそこらじゅうでバンドがブルースをやってたんです。そんなんは、ええなぁと思いました。ほんで、みんなすごくアドリブが多くて、演奏を楽しんでるなぁとも思いました」。
デビューしてから、ライブイベントはもちろん、テレビやラジオ、CM、映画のテーマソングなど、あげ出したらキリがない程、引っ張りだこの状態が続く。しかし、バンドは90年代に入ると、メンバーそれぞれにやりたいことがでてきて、木村さんもソロアルバムを発表した。同時に、バンドとしてレコードを無理に出して行くことにも疑問を感じる様になっていく。
デビューアルバムとなる“憂歌団”は、まさに楽しくてしょうがないという気持ちがストレートに伝わってくる傑作だ。元々、そのライブのスゴさからメジャーにまで上り詰めたバンド。本編90分、アンコール90分といった、今では信じられない、筋書きのないパフォーマンスを披露し続けるなど、まさに唯一無二のブルースバンドとしてシーンに君臨した。また、88年に日本人バンドとして初めてシカゴ・ブルース・フェスティバルにも出演。日本にも本物のブルースバンドがいることを本場アメリカで証明してみせた。
「当時は日本語でブルースっていうのはあんまりなくて、ブルースは外国のモノという先入観があった。日本語のブルースはダサイっていうムードもあったけど、僕はそういう考え方の方がダサイ様な気がしたんです。日本語の方が歌う方も気持ちが入るし、聞く方もわかりやすいしね。とはいっても、アメリカのシカゴでやった時なんかは、日本語で歌っても現地の人は楽しんでくれたし、言葉を超えたところで分かりあえるんやとも思いました。イイものはイイ。そんなのをあっちへ行って実感しましたね。他に面白かったんは、大阪でいうところの青空カラオケみたいな感覚があっちにもあって、街のそこらじゅうでバンドがブルースをやってたんです。そんなんは、ええなぁと思いました。ほんで、みんなすごくアドリブが多くて、演奏を楽しんでるなぁとも思いました」。
デビューしてから、ライブイベントはもちろん、テレビやラジオ、CM、映画のテーマソングなど、あげ出したらキリがない程、引っ張りだこの状態が続く。しかし、バンドは90年代に入ると、メンバーそれぞれにやりたいことがでてきて、木村さんもソロアルバムを発表した。同時に、バンドとしてレコードを無理に出して行くことにも疑問を感じる様になっていく。
「バンドを始めた頃は、みんな楽しんどった。そのうち、やらなあかんことが多くなって、最後の方は惰性でやってる感じになってしまった。ポンポン楽曲が出来るタイプでもなかったしね。ちょうど40歳前で、好きでもないもんを歌いたくないし、何してんやろなぁってね。そうゆう状況に対しても、バンドのメンバーでそれぞれ意見は違うし、やっぱり、みんな個性あるしね…」。98年、20年以上活動して来た憂歌団は突然の休眠宣言。ソロ活動は、94年からスタートしていたが、冒頭の言葉の通り、木村さんは、ただ自由に楽しく歌いたいという、ブルースの原点を突き詰めて行く。年間100本以上ものライブを全国各地で行い、様々なアーティストとコラボし、ソロからベストまでを含む14枚ものアルバムをリリース。会場も居酒屋や温室、神社など、ユニークなロケーションが多いのは、きっとギター1本だけでもその場を木村ワールドに変えられるという自負心があればこそ。そして、バンド休眠宣言から15年の年月が経ち、2013年に憂歌団は再スタート。「みんな相変わらず。でも、今の自分らでも違和感なく楽しめる楽曲があるというのはありがたいこと」。インタビューを通して“自分がいかに楽しんでやるか”という言葉が繰り返し語られた。そんな姿勢は音楽だけでなく、ファッションにも通じるところがある。「やっぱりファッションも楽しむことやと思います。僕らの時で言うと、学生帽ひとつとっても好きに被りたいみたいに。校章を古く見せるとかもありましたね。個人的には、みんなと同じなんが好きじゃなくて、やっぱり個性を出したい。でも奇抜なのも好きじゃない。となると、みんなが綺麗な洋服を着ていたら、ボロボロなんを着るとか、タイミングを楽しむっちゅうかね。お腹いっぱいの時にご飯出されたら嫌やけど、腹減ってる時やったら嬉しいみたいな。タイミングって歌を歌う時にも大事で、また楽しいトコロでもありますね」。
取材当日も自転車に乗ってふらりと登場した木村さん。生まれた街、大阪市生野区という下町を愛し、家族や友人との生活の中で、ブルースに出会い、日本が誇るスペシャルなヴォーカリストとなった。ブルースという音楽は、50代、60代から何とも言えない味わいが出て、さらに良くなると言われているが、木村さんはちょうどその時期にあたる61歳。
取材当日も自転車に乗ってふらりと登場した木村さん。生まれた街、大阪市生野区という下町を愛し、家族や友人との生活の中で、ブルースに出会い、日本が誇るスペシャルなヴォーカリストとなった。ブルースという音楽は、50代、60代から何とも言えない味わいが出て、さらに良くなると言われているが、木村さんはちょうどその時期にあたる61歳。


数ある憂歌団/木村充揮作品から、
ネペンテス清水慶三の愛聴盤をピックアップ 「憂歌団」
「憂歌団」
ハタチそこそことは思えない
完成度の記念すべき1stアルバム 「生聞59分」
「生聞59分」
ライブバンドとしての魅力が詰まった
憂歌団の初のライブアルバム 「小さな花」
「小さな花」
甲本ヒロトによる楽曲や名曲
「ケサラ」が話題となったソロアルバムnepenthes©2006.AllRightsReserved.